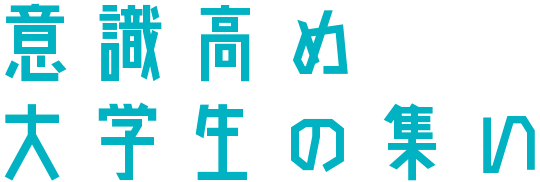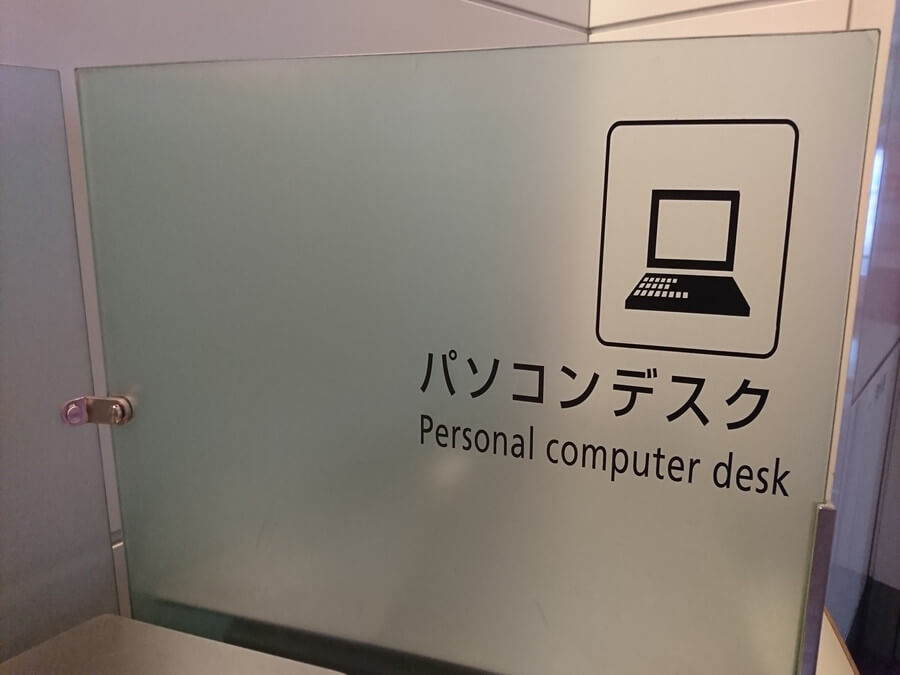
卒論とは
大学生活の総括として作成をするのが卒業論文です。
卒論はだいたい卒業年度の2月下旬~3月始めが提出期限になっているので、だいたいどの大学でも1月中までには研究を完成させて、約1ヶ月をかけて文章をまとめるということになります。
ただ、卒論はレポートのように一発で出してOKをもらうということはなく、まずは草稿を作って指導教官に見てもらい、そこで修正点を受けて何度か書き直すということになりますので、作成にはかなり時間がかかります。
十分に時間があるつもりであっても、そうしたリテイクを何度も重ねていくとかなり時間がかかっていくので、結果的に提出期限ギリギリで攻防をすることになるという人が多くなるのです。
現在では卒論の提出はワープロソフトなどで出力したもの、もしくはデータそのものとなっていると思いますので、何度かやり直しがあったときにすぐに修正ができるようにしっかりバックアップをとり、素早く対応できるようにしておくのがよい方法と言えます。
複数のパソコンで作成することもありますので、共通して使用できるアプリケーションを選ぶことも大切です。
卒論の基本的な書き方、ポイント、注意点
卒業論文は学科や研究の内容にもよりますが、ほとんどの場合でA4用紙に12ポイントで記入したとして20ページ程度にまでなります。
提出された論文は担当の教授のみが読むのではなく、複数の学科教員の間で回覧されることになります。
しかし熱心に力を入れて書いた卒論であっても、その隅々までをすべての教員が読むというわけではなく、大抵がその概要によって成績を判定されるのです。
そのため、無難に卒業できるような卒論に仕上げたいという場合は、まず論文としての体裁をしっかりと守り、「手抜き」と思われないように仕上げることが重要になってきます。
理系と文系のように専攻が異なると卒論の形式も異なりますが、ほとんどの場合「表紙」「概要」「目次」「本論」「結論」「付録」「参考文献」といったような順番で記載していくことになります。
この時、もっとも力を入れてもらいたいのが「概要」です。
論文なんだから「本論」に力を入れるべきではないの?と言われるかもしれませんが、前述したように卒論という長い文章は、すべて完璧に目を通してもらえるわけではありません。
そこで、できるだけ早くに目を通したいと思う教授や先生が重要視するのが「概要」です。
「概要」がしっかりと作られている卒論は、本論のどの部分をよく見ればよいかということが先に分かりますので、その卒論自体がどういったことを言いたくて書かれたかを短時間で理解することができます。
本論をしっかり書けば概要は適当でもよいという考えがもっとも良くなく、概要に手抜きが感じられるとそれだけで卒論そのものの評価も低くなってしまいます。